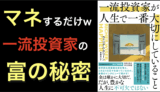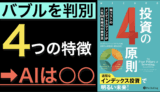ロバート・シラー著『根拠なき熱狂』は、2000年に出版され、ITバブル崩壊直前の株式市場の異常を鋭く予見した書籍として知られています。
本書のタイトルは、当時のFRB議長アラン・グリーンスパンの言葉「根拠なき熱狂」に由来し、その先見性と警告性から高く評価されました。
この記事では、その第2章にある「ITバブルの12の要因」を中心に、現代の株式市場と比較しながら本書の重要性を再確認します。
①インターネットとAI:新技術への期待と懸念
第1の要因は「インターネットの到来」ですが、これは現在のAIブームと非常に似ています。当時の人々がインターネットに感じた革新性と同様、今日ではChatGPTなどAIの進化が広く認識され、その影響は既存企業との競合や市場構造の変化に及んでいます。AIが株式市場全体の利益にどのように貢献するかは未知数ですが、技術革新に対する期待感は、株価を押し上げる大きな要因になっています。
②経済的ライバルの衰退とアメリカ優位
2つ目は「経済的ライバルの衰退」。
2000年当時の日本やソ連のように、現在では中国の経済成長鈍化や不動産バブル崩壊が注目されています。これにより、相対的にアメリカの経済的優位性が高まり、米株への資金流入が進んでいるとも言えるでしょう。
③ビジネス的成功を尊重する文化と投資熱の助長
3つ目は「ビジネス的成功の尊重」。
現代はイーロン・マスクに代表されるように、成功した起業家が社会的に高く評価される傾向が強まっています。
20年前に比べて、こうした文化が投資家の心理に影響を与え、株式市場への期待感をさらに高めているといえます。
④共和党優位の議会とキャピタルゲイン減税政策
4つ目の「共和党優位の議会とキャピタルゲイン減税」では、将来的な税制優遇が投資家に株の売却を控えさせる心理を生んでいます。
これは現在のビットコイン投資と同様に、税制の変化が市場参加者の行動に影響を与える例だといえます。
⑤ベビーブーマーと資産市場への影響
5つ目の要因「ベビーブーマーの影響」では、裕福な世代が資産市場に与える影響が取り上げられています。
住宅価格の上昇や資産保有の集中など、現代でもこの世代が市場を支えている部分が大きいことは間違いありません。
⑥メディアと投資参加の拡大
6つ目は「メディアのビジネスニュースの拡大」
SNSやYouTubeといった現代の情報発信媒体は、初心者投資家の市場参加を促し、結果として市場全体の活性化に繋がっています。これは、当時の新聞やテレビと同様の役割を担っているといえます。
⑦アナリストの強気姿勢と楽観心理
7つ目「楽観色を強めるアナリスト」では、株式買い推奨の偏りが市場の過熱を招いた事例が紹介されています。
現在もこの傾向は見られ、過度な楽観は市場のバブル化を助長する要因といえます。
⑧確定拠出年金と投資信託の成長
8つ目は「確定拠出年金プランの拡大」。401Kに代表される年金制度の変化は、日本の新NISAとも類似しています。
専門家による運用への信頼が、個人の市場参加を後押ししている構図は、今も変わらず続いています。
⑨ニューチュアルファンドの拡大
世界的にパッシブ運用のインデックスファンドの資産額が拡大しています。
メディアや広告に力も相まって、多くの投資初心者がインデックスファンドに向かう現状は、バブルの様相です。
⑩インフレ抑制とマネー幻想
10番目「インフレ抑制とマネー幻想」は、2000年当時の低インフレが株価上昇に寄与した背景が説明されています。
現代はむしろインフレの高まりの中で株価が上昇しており、異なるメカニズムが働いている点が興味深いです。
11〜12:取引量とギャンブル的投資
11番目と12番目は「取引量の拡大」と「ギャンブル機会の増大」。
オンライントレードや暗号資産、ミームコインの台頭により、投機的な取引が増加し、価格変動の大きな一因となっています。
まとめ:分散投資と心理の重要性
本書の終盤では「厳密な価格など存在しない」という示唆的な言葉で締めくくられています。
株式市場は心理によって動くものであり、常に適正価格を保っているとは限りません。したがって、暴落のリスクを避けるためには、特定の資産に偏らない「分散投資」が基本となるべきです。
今後の市場がどうなるかは誰にも予測できませんが、シラーの指摘した12の要因を理解することで、冷静な投資判断の一助となると思います。