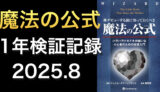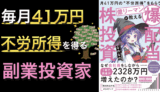『野生の経済額で読み解く投資の最適解』(日本実業出版社)は、著者による8年ぶりの新刊として注目を集めています。本書では、日本のデフレ脱却や金融政策の変遷、インフレ期待を踏まえた投資戦略が詳しく解説されており、特に日本株で勝ちたい投資家にとって必読の一冊です。
日本がインフレに入ったと判断できる4つの理由
著者は、日本がインフレ局面に突入したと判断できる4つの理由を挙げています。
①供給ショック
1つ目は海外からのインフレの波が日本に届くのに3年かかるという供給ショックの構造です。エネルギーや食品など輸入品の価格上昇が企業物価に影響し、それがやがて消費者物価に波及する仕組みです。
②賃金上昇圧力
2つ目は、賃金に対するデフレ圧力が緩和されたこと。団塊の世代の引退が進み、低賃金労働者の割合が減少。さらに段階ジュニア世代が高年収層にシフトしつつあり、賃金上昇圧力が高まっています。
③製造業の国際競争力
3つ目は、日本の製造業が国際競争力を維持しつつある点。
④住宅用不動産価格
4つ目として、住宅用不動産価格が上昇トレンドに入っていることが、長期的なインフレ期待を示しています。
金融政策の変遷とフォワードガイダンスの必要性
本書では、アメリカFRBの金融政策の歴史的変遷も紹介されており、現代の政策がどのようにして形成されてきたかを学ぶことができます。特に注目すべきは、2012年以降に導入されたフォワードガイダンス(将来の政策方針の事前提示)です。
この制度により、市場の不確実性が低下し、VIX指数(恐怖指数)の平均値が低下したことが説明されています。著者は、日本においても同様の制度導入が必要であるとし、日銀の政策に透明性と合理性を持たせることで、円安や金融市場の不安定化を防ぐべきだと提案しています。
絶対的価値と相対的価値から読み解く株式投資
投資における「絶対的価値」とは、企業の利益や資産価値そのものを指し、EPSやBPSといった財務指標で測られます。一方で「相対的価値」は、金利や為替など外部環境との比較によって決まり、株式投資の魅力が変動します。
現行の金融体制では、FRBの政策発表が市場に強い影響を与えるため、金利上昇が直接的に株価に影響しやすくなっています。つまり、投資判断においては、企業の実力だけでなく、マクロ経済や政策動向を見極める力が必要不可欠なのです。
日本株投資の新フェーズと今後の戦略
日本株市場は、これまでのデフレ環境から一転、インフレ時代へと突入しています。そのため、従来の投資戦略では通用しない局面が増えてきました。著者は、インフレ環境下で有効な日本株投資戦略を4つ提示しており、資産形成を図るためにはフェーズに応じた戦略の再構築が必要であると述べています。
- アルファだけでなくベータも取りに行く
- 短期トレードではなく長期ポートフォリオの構築
- 良い“資産”を持つ企業が選ばれる
- イノベーションはあらゆる分野で発生する
以上の4つですが、まず、「ベータ」を取るのは、指数連動のインデックスファンドをある程度もつことで対応できそうだと思います。
長期ポートフォリオは当然ですね。私も基本は長期の姿勢をとっています。次に大事だとおもったのが、「良い資産」ということです。「資産バリュー株」を探すのは良い戦略のように感じます。
最近でいえば、たーちゃんさんも資産バリュー株の有効性を語っていたし、かぶ1000さんとかの参考書もあるので、資産バリュー株を見直してみようかなあ。
また、日本の政策金利についても適正な中立金利水準の検討が求められており、過度な金融緩和による副作用についても考慮する時期に来ています。
特に変動金利で住宅ローンを組んでいる層にとっては、金利の動向が生活に直結する問題であり、注意が必要です。
本書は投資中級者以上を対象とした内容であり、初心者にとっては難解に感じる部分もあるかもしれません。
しかし、現代日本の経済構造や投資環境を理解するうえで極めて有益な知見が詰まっています。日本株に本格的に取り組みたい方は、ぜひ本書を手に取ってみてはいかがでしょうか。